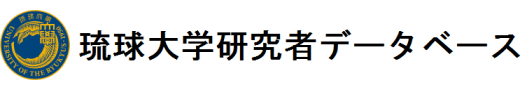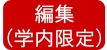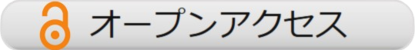|
職名 |
准教授 |
|
科研費研究者番号 |
50396925 |
|
ホームページ |
|
|
|
|
出身大学院 【 表示 / 非表示 】
-
-2001年03月
東京大学 理学研究科 化学専攻 修士課程 修了
-
-2004年03月
北海道大学 理学研究科 地球惑星科学専攻 博士後期課程 修了
職歴 【 表示 / 非表示 】
-
2007年04月-2015年04月
琉球大学 理学部 海洋自然科学科 化学系 助教
-
2015年05月-継続中
琉球大学 理学部 海洋自然科学科 化学系 准教授
所属学会・委員会 【 表示 / 非表示 】
-
2000年04月-継続中
日本地球化学会
-
2001年04月-継続中
日本地質学会
-
2002年04月-継続中
アメリカ地球物理学連合
-
2015年06月-継続中
日本海水学会
学位論文 【 表示 / 非表示 】
-
Geochemical studies on the origin of methane in crustal fluids using carbon isotopes of methane and carbon dioxide as tracers
2004年03月
論文 【 表示 / 非表示 】
-
Tomohiro Toki, Tasuku Nohara, Yoshiaki Urata, Ryuichi Shinjo, Shuko Hokakubo-Watanabe, Jun-ichiro Ishibashi, and Shinsuke Kawagucci (担当範囲: 研究全般)
Progress in Earth and Planetary Science ( Springer Nature ) 9 ( 1 ) 59 2022年11月 [ 査読有り ]
掲載種別: 研究論文(学術雑誌)
-
この論文にアクセスする
-
-
Origin of helium in basement rocks and carbonate veins in Yonaguni Island
Toki, T; Yasumura, K; Takahata, N; Miyajima, Y; Miyaki, H; Oohashi, K; Otsubo, M
GEOCHEMICAL JOURNAL ( 一般社団法人日本地球化学会 ) 58 ( 6 ) 293 - 303 2024年 [ 査読有り ]
掲載種別: 研究論文(学術雑誌)
-
この論文にアクセスする
-
関連情報を調べる
-
-
Asada, M; Yamashita, M; Fukuchi, R; Yokota, T; Toki, T; Ijiri, A; Kawamura, K
FRONTIERS IN EARTH SCIENCE ( Frontiers in Earth Science ) 11 2023年11月 [ 査読有り ]
掲載種別: 研究論文(学術雑誌)
-
この論文にアクセスする
-
-
Distribution of dissolved methane in seawater from the East China Sea to the Ryukyu forearc
Toki, T; Chibana, H; Shimabukuro, T; Yamakawa, Y
FRONTIERS IN EARTH SCIENCE ( Frontiers in Earth Science ) 11 2023年11月 [ 査読有り ]
掲載種別: 研究論文(学術雑誌)
-
この論文にアクセスする
-
-
Mitsutome, Y; Agena, K; Toki, T; Song, KH; Shinjo, R; Ijiri, A
FRONTIERS IN MARINE SCIENCE ( Frontiers in Marine Science ) 10 2023年09月 [ 査読有り ]
掲載種別: 研究論文(学術雑誌)
-
この論文にアクセスする
-
著書 【 表示 / 非表示 】
-
海底熱水鉱床調査技術プロトコル : 戦略的イノベーション創造プログラム : SIP『次世代海洋資源調査技術』 (海のジパング計画)
石橋 純一郎, 正木 裕香, 岡村 慶, 野口 拓郎, 土岐 知弘, 新城 竜一 ( 担当: 共著 , 担当範囲: 地質調査で採取された堆積物試料中の間隙水の地球化学的解析 )
国立研究開発法人海洋研究開発機構次世代海洋資源調査技術研究開発プロジェクトチーム 2018年11月 ( ページ数: 59 , 担当ページ: p.52 )
-
琉球列島の自然講座 サンゴ礁・島の生き物たち・自然環境
土岐 知弘 ( 担当: 単著 , 担当範囲: 海底熱水研究なう@沖縄トラフ )
ボーダーインク 2015年03月 ( ページ数: 207 , 担当ページ: p.160-161 )
-
Nature in the Ryukyu Archipelago
Tomohiro Toki ( 担当: 単著 , 担当範囲: When do you research hydrothermal systems? Now! )
Change and Coral Reef/Island Dynamics Faculty of Science, University of the Ryukyus 2015年 ( ページ数: 154 , 担当ページ: p.120-121 )
-
潜水調査船が観た深海生物ー深海生物研究の現在
石橋 純一郎, 土岐 知弘 ( 担当: 共著 , 担当範囲: 分担執筆 )
東海大学出版会 2008年02月 ( ページ数: 487 , 担当ページ: p.10-22 )
-
海のトリビア
中山 典子,土岐 知弘 ( 担当: 分担執筆 , 担当範囲: 海底下には火をつけると燃える氷が存在する )
日本教育新聞社出版局 2005年03月 ( ページ数: 115 , 担当ページ: p.28-29 )
MISC(その他業績・査読無し論文等) 【 表示 / 非表示 】
-
マルチアイソトープを用いた沖縄県辺戸岬におけるエアロゾルの起源の解明
土岐 知弘,河野 彩香,申 基澈
地学雑誌 ( 東京地学協会編集委員会 ) 132 ( 6 ) N99 - N99 2023年12月
-
泥火山研究における地球化学の役割と課題
土岐 知弘
琉球大学理学部紀要 ( 琉球大学理学部 ) ( 108 ) 1 - 26 2020年03月
-
沖縄トラフ海底熱水系研究30年史
土岐 知弘
月刊海洋号外(海洋システムの謎に挑む化学 : 蒲生俊敬教授退職記念号 : 総特集) ( 海洋出版 ) 61 174 - 179 2018年05月
研究発表等の成果普及活動 【 表示 / 非表示 】
-
Indigenous traditions and water governance: The case of the Erfeng irrigation canal
Miyuki Shimabukuro, Tomohiro Toki, Yoshiaki Kubo, Hitoshi Shimabukuro
The 2nd International Sociohydrology Conference (東京大学・本郷キャンパス) 2025年07月 - 2025年07月
-
能登半島地震の震源域周辺における表層堆積物中のホウ素の起源深度
土岐 知弘,森永 燿平,新城 竜一,Zandvakili Zahra,西尾 嘉朗,鹿児島 渉悟,大塚 進平,張 勁,小林 祐大,井尻 暁,朴 進午,KH-24-E1乗船研究者一同
日本地球惑星科学連合2025年大会 (幕張メッセ) 2025年05月 - 2025年05月
-
琉球海溝北部海底泥火山群における海底下深部流体の供給
山田 貫太郎,土岐 知弘,石川 剛志,石橋 純一郎,大塚 宏徳,板木 拓也,村山 雅史,井尻 暁
日本地球惑星科学連合2025年大会 (幕張メッセ) 2025年05月 - 2025年05月
-
Origin of lithium in pore fluids near offshore fault zone, northern Noto Peninsula, two months after the 2024 Noto Peninsula earthquake (M7.6) during the R/V Hakuho-maru cruise
Zahra Zandvakili, Yoshiro Nishio, Tomohiro Toki, Takanori Kagoshima, Jin-Oh Park
日本地球惑星科学連合2025年大会 (幕張メッセ) 2025年05月 - 2025年05月
-
Anomaly of concentration and isotope ratio of Mo and W in hydrothermal fluids at a back-arc basin, Okinawa Trough
Matsuoka Kohei, Sohrin Yoshiki, Shotaro Takano, Shinsuke Kawagucci, Tomohiro Toki
日本地球惑星科学連合2025年大会 (幕張メッセ) 2025年05月 - 2025年05月
論文査読・海外派遣等、研究諸活動 【 表示 / 非表示 】
-
海洋科学・同位体地球化学に関する講義と共同研究
研究者招聘
2018年09月 -
ピアレビュー
学術論文査読件数
2004年04月-継続中
科研費獲得情報 【 表示 / 非表示 】
-
海山の沈み込みは巨大地震域の固着を弱めるか:南海トラフの2海山での検証
基盤研究(S)
課題番号: 24H00020
研究期間: 2024年04月 - 2029年03月
代表者: 木下 正高, 仲田 理映, 荒木 英一郎, 橋本 善孝, 濱田 洋平, 土岐 知弘, 澤井 みち代
直接経費: 152,900,000(円) 間接経費: 198,770,000(円) 金額合計: 45,870,000(円)
-
海底泥火山活動が繋ぐ地圏-水圏-生命圏:深部生命・炭素の海洋拡散過程とその影響
基盤研究(A)
課題番号: 24H00273
研究期間: 2024年04月 - 2029年03月
代表者: 井尻 暁, 星野 辰彦, 乙坂 重嘉, 村山 雅史, 土岐 知弘, 渡部 裕美, 野口 拓郎, 大塚 宏徳
直接経費: 36,800,000(円) 間接経費: 47,840,000(円) 金額合計: 11,040,000(円)
-
東シナ海大陸斜面域におけるメタンの供給源は,熱水か?
基盤研究(C)
課題番号: 23K11391
研究期間: 2023年04月 - 2027年03月
代表者: 土岐 知弘
直接経費: 3,600,000(円) 間接経費: 4,680,000(円) 金額合計: 1,080,000(円)
-
沈み込むプレート上部における水の流動の地域による違いとプレート境界への影響の解明
基盤研究(B)
課題番号: 23H01268
研究期間: 2023年04月 - 2026年03月
代表者: 山野 誠, 木下 正高, 笠谷 貴史, 後藤 忠徳, 朴 進午, 土岐 知弘, 川田 佳史
直接経費: 14,400,000(円) 間接経費: 18,720,000(円) 金額合計: 4,320,000(円)
-
海底泥火山活動を介した地下深部生命、炭素の海洋への拡散・循環モデルの構築
基盤研究(B)
課題番号: 20H04315
研究期間: 2020年04月 - 2023年03月
代表者: 井尻 暁, 星野 辰彦, 乙坂 重嘉, 村山 雅史, 土岐 知弘, 野口 拓郎
直接経費: 13,500,000(円) 間接経費: 17,550,000(円) 金額合計: 4,050,000(円)
その他研究費獲得情報 【 表示 / 非表示 】
-
沖縄県内の湧水の滞留時間に基づいた渇水時に強い湧水の指定
研究費種類: 財団・社団法人等の民間助成金 参画方法: 研究代表者
研究種別: 研究助成 事業名: 公益信託 宇流麻学術研究助成基金
研究期間: 2024年10月 - 2025年08月
代表者: 土岐 知弘 資金配分機関: (公財)沖縄県国際交流・人材育成財団
直接経費: 260,000(円) 間接経費: 0(円) 金額合計: 2,600,000(円)
-
マルチアイソトープを用いた沖縄県辺戸岬におけるエアロゾルの起源の解明
研究費種類: 財団・社団法人等の民間助成金 参画方法: 研究代表者
研究種別: 研究助成 事業名: 令和4年度調査・研究および国際研究集会助成金
研究期間: 2022年07月 - 2023年03月
代表者: 土岐 知弘 連携研究者: 河野 彩香 資金配分機関: 公益社団法人 東京地学協会
直接経費: 500,000(円) 間接経費: 0(円) 金額合計: 500,000(円)
-
ボードゲームを用いた南の島特有の水管理・利用の在り方に関する合意形成プロセスの解明
研究費種類: 財団・社団法人等の民間助成金 参画方法: 研究代表者
研究種別: 研究助成 事業名: 2022年度調査研究助成
研究期間: 2022年03月 - 2025年02月
代表者: 土岐 知弘 連携研究者: 島袋 美由紀 資金配分機関: 公益財団法人 科学技術融合振興財団
直接経費: 1,500,000(円) 間接経費: 0(円) 金額合計: 1,500,000(円)
-
陸と海をつなぐ水循環を軸としたマルチリソースの順応的ガバナンス: サンゴ礁島嶼系での展開
研究費種類: 公的研究費(省庁・独法・大学等) 参画方法: 研究分担者
研究種別: その他 事業名: 実践プロジェクト
研究期間: 2019年04月 - 2027年03月
資金配分機関: 総合地球環境学研究所
-
亜熱帯島嶼の持続可能な水資源利用に向けた参画・合意に基づく流域ガバナンスの構築
研究費種類: 公的研究費(省庁・独法・大学等) 参画方法: 研究分担者
研究種別: 研究助成 事業名: JST SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム
研究期間: 2019年04月 - 2023年03月
代表者: 安元 純 連携研究者: 新城 竜一 資金配分機関: 国立研究開発法人科学技術振興機構
直接経費: 23,000,000(円)
共同研究実施実績 【 表示 / 非表示 】
-
東シナ海大陸斜面域におけるメタン湧出のメカニズムの解明
研究期間: 2024年04月 - 2025年03月
代表者: 土岐 知弘 連携研究者: 高畑 直人 資金配分機関: 東京大学
直接経費: 100,000(円) 金額合計: 100,000(円)
-
琉球海溝北部海底泥火山群の表層堆積物中の希ガスの起源の多様性
研究期間: 2023年04月 - 2024年03月
代表者: 土岐 知弘 連携研究者: 井尻 暁 資金配分機関: 東京大学
直接経費: 100,000(円) 金額合計: 100,000(円)
-
福徳岡ノ場から漂着した軽石中のヘリウム同位体比の時系列変動
研究期間: 2022年04月 - 2023年03月
代表者: 土岐 知弘 連携研究者: 佐野 有司 資金配分機関: 東京大学
直接経費: 100,000(円) 金額合計: 100,000(円)
-
与那国島サンニヌ台正断層域に分布するカルサイト中のヘリウム同位体比
研究期間: 2021年04月 - 2022年03月
代表者: 土岐 知弘 連携研究者: 白井 厚太郎 資金配分機関: 東京大学
直接経費: 100,000(円) 金額合計: 100,000(円)
-
種子島沖海底泥火山群からの物質・流体フラックスの定量的見積もり
研究期間: 2020年04月 - 2021年03月
代表者: 土岐 知弘 連携研究者: 佐野 有司 資金配分機関: 東京大学
直接経費: 100,000(円) 金額合計: 100,000(円)
年度別外部資金獲得額 【 表示 / 非表示 】
-
2022年度 基盤A,東京地学協会,FOST 3500000円
-
2012年度 新学術領域 3000000円
-
2015年度 萌芽 1900000円
-
2016年度 地域志向推進経費,萌芽 2046755円
-
2017年度 萌芽 525879円
担当授業科目(学内) 【 表示 / 非表示 】
-
2025年度 化学実験 実験・実習・実技 主担当
-
2025年度 化学実験 実験・実習・実技 主担当
-
2025年度 海洋化学概論 講義 主担当
-
2025年度 卒業研究II 実験・実習・実技 主担当
-
2025年度 卒業研究I 実験・実習・実技 主担当
学外の社会活動(高大・地域連携等) 【 表示 / 非表示 】
-
ボードゲーム“すいまーる”
山梨大学・山梨大学国際流域環境研究センター 地域資源ラボ
2025年03月




-
ボードゲーム“すいまーる”
西原小学校 総合学習
2024年12月




-
ボードゲーム“すいまーる”
久米島西中学校 総合学習
2024年12月




-
わくわく湧き水クイズ!
沖縄地域公共政策研究会すいまーるプロジェクト 2024年「水の日」祝祭・水ぬぐすーじさびら!
2024年08月




-
ワークショップ“すいまーる”
JICA沖縄 2024年度JICA国際理解・開発教育 第1回指導者養成講座/教師海外研修第2回事前研修
2024年07月




メディア報道 【 表示 / 非表示 】
-
「流体」の謎…海底の泥を分析 テレビ・ラジオ番組
㈱テレビ朝日 サンデーステーション 2024年3月
執筆者: 本人以外