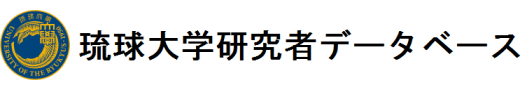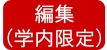|
職名 |
教授 |
|
科研費研究者番号 |
20301393 |
職歴 【 表示 / 非表示 】
-
1998年10月
- , University of the Ryukyus, University Education Center, Associate Professor
-
1998年10月
- , 琉球大学 大学教育センター 准教授
-
1998年10月-継続中
琉球大学 大学教育センター 准教授
-
2018年04月-継続中
琉球大学
論文 【 表示 / 非表示 】
-
沖縄の子どもたちの学力と教職員のメンタルヘルス
西本 裕輝
日本教育心理学会総会発表論文集 ( 一般社団法人 日本教育心理学会 ) 65 ( 0 ) 350 2023年
掲載種別: 研究論文(学術雑誌)
-
この論文にアクセスする
-
関連情報を調べる
-
-
小学校におけるデジタル化と学力
西本 裕輝
中央教育研究所編『小学校教員の教育観とこれからの教育 ─デジタル化の流れの中で─』 98 49 - 53 2022年
掲載種別: 研究論文(学術雑誌)
-
関連情報を調べる
-
-
子どもたちに早期にタブレットを与えることの危険性
西本 裕輝
中央教育研究所編『小学校教員の教育観とこれからの教育 ─デジタル化の流れの中で─』 98 175 - 176 2022年
掲載種別: 研究論文(学術雑誌)
-
関連情報を調べる
-
-
沖縄県の小中学生おける国語の自律学習動機づけ、学習方略、言語能力に関する実態調査:低学力問題の解決に向けてー
西本 裕輝
琉球大学教育学部紀要 94 75 - 83 2019年 [ 査読有り ]
掲載種別: 研究論文(学術雑誌)
-
関連情報を調べる
-
著書 【 表示 / 非表示 】
-
沖縄で教師をめざす人のために
上地, 完治, 西本, 裕輝 ( 担当: その他 )
協同出版 2015年07月 ( ページ数: 304p )
MISC(その他業績・査読無し論文等) 【 表示 / 非表示 】
-
西本 裕輝, 崎山 弥生, 亀川 怜, 服部 洋一, Nishimoto Hiroki, Sakiyama Yayoi, Kamekawa Satoi, Hattori Yoichi
琉球大学教育学部紀要 ( 琉球大学教育学部 ) 96 29 - 34 2020年02月 [査読有り]
-
沖縄県の小中学生における国語の自律的学習動機づけ,学習方略,言語能力に関する実態調査 : 低学力問題の解決に向けて
阿波連 憲太, 西本 裕輝, Aharen Kenta, Nishimoto Hiroki
琉球大学教育学部紀要 ( 琉球大学教育学部 ) 94 75 - 83 2019年03月
-
琉球大学学士課程における退学・休学・除籍・留年の早期発見に向けた検討 : 退学等に至る学生の初年次前期のGPAと入学動機の特徴の可視化の試み
高橋 望, 藤本 裕介, 西本 裕輝
琉球大学大学教育センター報 = University Education Center Bulltein ( 琉球大学大学グローバル教育支援機構 ) ( 21 ) 89 - 100 2019年03月
科研費獲得情報 【 表示 / 非表示 】
-
沖縄の小中学生の学力問題解決のための追跡調査研究~静岡との比較を中心に~
基盤研究(C)
課題番号: 21K02312
研究期間: 2021年04月 - 2025年03月
代表者: 西本 裕輝
直接経費: 3,100,000(円) 間接経費: 4,030,000(円) 金額合計: 930,000(円)
-
沖縄の小中学生の学力向上に関する実証的研究~離島・へき地支援を中心に~
基盤研究(C)
課題番号: 16K04612
研究期間: 2016年04月 - 2019年03月
代表者: 西本 裕輝
直接経費: 3,500,000(円) 間接経費: 4,550,000(円) 金額合計: 1,050,000(円)
-
沖縄の小中学生の学力向上に関する実証的研究~離島・へき地支援を中心に~
基盤研究(C)
課題番号: 16K04612
研究期間: 2016年04月 - 2019年03月
代表者: 西本 裕輝
直接経費: 3,500,000(円) 間接経費: 1,050,000(円) 金額合計: 4,550,000(円)
-
沖縄の小中学生の学力向上に関する実証的研究~離島・へき地支援を中心に~
基盤研究(C)
課題番号: 16K04612
研究期間: 2016年04月 - 2019年03月
代表者: 西本 裕輝
直接経費: 3,500,000(円) 間接経費: 4,550,000(円) 金額合計: 1,050,000(円)
-
沖縄の小中学生の学力向上に関する実証的研究~離島・へき地支援を中心に~
基盤研究(C)
課題番号: 16K04612
研究期間: 2016年04月 - 2019年03月
代表者: 西本 裕輝
直接経費: 3,500,000(円) 間接経費: 4,550,000(円) 金額合計: 1,050,000(円)