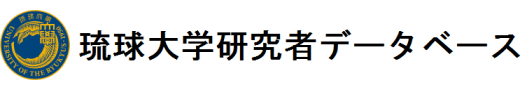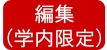|
職名 |
准教授 |
|
科研費研究者番号 |
30837513 |
論文 【 表示 / 非表示 】
-
其理似尚未備―曹廷杰『万国公法釈義』における『万国公法』の儒学的再解釈について
望月 直人
『近現代中国の制度とモデル: 京都大学人文科学研究所附属現代中国研究センター研究報告書』 335 - 363 2025年02月 [ 査読有り ]
掲載種別: 研究論文(その他学術会議資料等)
-
中国の国際法基本原則:ソビエト、欧米、中国の国際法理論の比較
望月直人, 藥袋 佳祐
アメリカン大学国際法レビュー 39 ( 2 ) 171 - 217 2024年09月 [ 査読有り ]
掲載種別: 研究論文(学術雑誌)
-
国際法と「(万国)公法」のあいだ -朱克敬『公法十一篇』の検討-
望月 直人
地理歴史人類学論集 ( 琉球大学国際地域創造学部地域文化科学プログラム ) ( 13 ) 1 - 31 2024年03月 [ 査読有り ]
掲載種別: 研究論文(その他学術会議資料等)
-
この論文にアクセスする
-
関連情報を調べる
-
-
「中國武員無端生事」 -李揚才事件(1878‐79年)に関する一考察-
望月 直人
地理歴史人類学論集 ( 琉球大学国際地域創造学部地域文化科学プログラム ) ( 12 ) 76 - 92 2023年03月 [ 査読有り ]
掲載種別: 研究論文(その他学術会議資料等)
-
この論文にアクセスする
-
-
「劉団の越塩」 ―19世紀雲南・ベトナム間における海塩密貿易と黒旗軍―
望月 直人
地理歴史人類学論集 ( 琉球大学国際地域創造学部地域文化科学プログラム ) ( 11 ) 1 - 17 2022年03月 [ 査読有り ]
掲載種別: 研究論文(その他学術会議資料等)
-
この論文にアクセスする
-